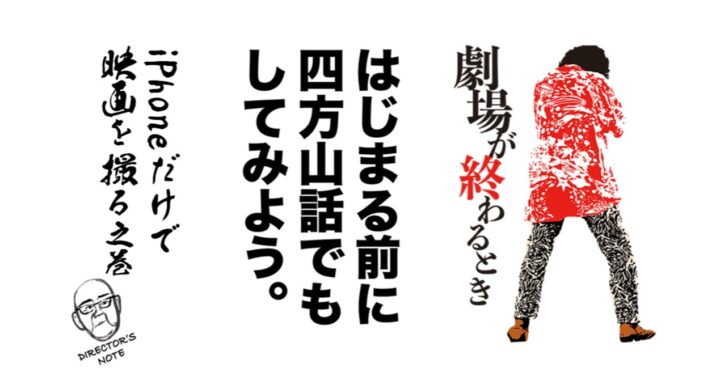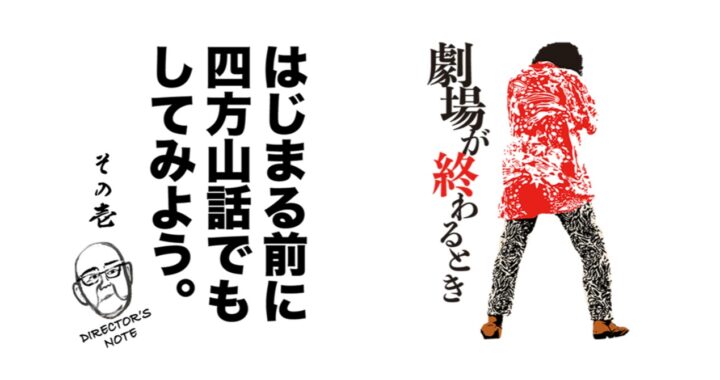映画を始めたころは、まじめに絵コンテを描いていた。脚本を元に撮影の構想を練り、スタッフがそれを見れば何をすればわかるようにと、細かい指示を書き込む。つまり撮影前に頭の中で映像を作り上げて、形にしていくわけだ。大学の映研時代から商業デビュー作の『パイナップルツアーズ』までは、それが映画の造り方だと思っていた。その確信に揺らぎが出たのは『パイナップルツアーズ』の完成後だった。
『パイナップルツアーズ』では、クレーンやレールなどの特殊機材を初めて使った。そういう機材を使って映画を撮るなんて「プロみたい」と、ついこのあいだまで学生監督だった僕は舞い上がって、複雑なショットを構想してワクワクし、現場で入念なリハーサルをして気合いを入れて映像を撮った。仕上がったカットを見て、しばらくは御満悦でもいられた。しかし、少し間をあけて、作品をビデオで見返していると、がんばった場面ほど飛ばして観てしまうことに気がついた。むしろ何度も見返すのは、主演の兼島麗子さんが洗面器で手を洗うだけのアップとか、深呼吸をする場面とか、役者が歩いている場面とか、シンプルな場面ばかりなのだ。
ようするに自分のイメージだけで作ったトリッキーな場面は、自分にとって驚きがない。頭の中で熟成したウンコを外に出したら、すっきりしたような…。例えが悪くて申し訳ないが、本当にそんな感じなのだ。役者に頼った部分、風景に頼った部分、何かに頼った部分は、見るたびに発見がある。なぜ自分がそれを選んで、それに魅かれ、それを撮ったのか、後からジワジワとわかってくる。
僕が完全に絵コンテを書かなくなったというか、描けずに撮影した最初の作品は、実は首里劇場で撮影した『UNDERCOVER JAPAN』(2003年)だった。
この企画は元々、AV監督のカンパニー松尾と、同じくAVからドキュメンタリーまで幅広く活躍する平野勝之が、クリスマスから初日の出までを、それぞれが東京と北海道で撮影するドキュメンタリー企画だった。しかしタイトルに「JAPAN」とあることから、沖縄も押さえようということになったらしく、当時は東京で暮らしていた僕に白羽の矢が立ったらしい。しかも撮影開始の三日前くらいのムチャぶりだった。
年末年始で里帰りの予定もあったし、やってみるかと引き受けてみたものの、何を撮ればいいのかわからずに僕は冬の沖縄をさまようことになる。そこで行き着いたのが学生時代に一度行ったことのある首里劇場だった。僕は特に何かを決めることなく、ダラダラと年末年始の成人映画館で過ごし、その日常、館長とのたわいのない会話、劇場で飼われていた小猫の映像を撮り続けた。とにかく、目の前の何かに反応しようと、良い感じで緊張感を保ちつつも、ゆるくて楽しい時間を過ごしていた。
東京に帰って編集を始めると、首里劇場に行き着くまでに、無理やりネタを作ろうとがんばった小細工や、慣れない一人語りはことごとくカットされていった。あざといギャクや、トリッキーでかっこいいカットも、時代を経たボロボロの劇場の存在感にはかなわないし、日だまりで毛繕いするだけの小猫にもかなわない。そうやっておもしろいと思える瞬間に、素直に反応し、一番良い光を捉えながら撮影したカットを繋いでいった結果、作品は濃縮されつつ、のほほんとした20分程度の短編となった。松尾、平野の両監督の作品と比べると、極端に短かいのだが、箸休め的なゆるさがウケた。とりあえず北海道-東京-沖縄を押さえた『UNDERCOVER JAPAN』という企画のミッションは無事に完了できた。もちろん、いまだに何度見返していても、自分自身が楽しめる作品になった。
もちろん、やりたい企画にもよるのだけど、自分が見つめていたいと思える対象と、それに反応する感覚。あと、ちょっとした技術的な知識があれば、こういう役者やロケ地とセッションするような身軽な映画の作り方が自分には向いているのだと実感した。そういう意味で、首里劇場は僕にとっては実践的な映画の学校でもあったのである。